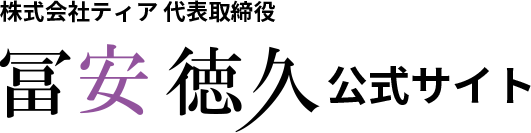逆説得 ~学歴より、感動~
第1章 十八歳で"天職"に出会う 3
やがて車は事務所に着いた。トラックに積んでいた荷物をおろして、整理整頓をして片づけ終わった後に、僕は藤田さんには何も言わずに、その足で事務所にいる店長のところに走って行った。
「すいません。店長、ちょっとお話があるんですが」
「何?どうした冨安君」
「じつはですね。僕、藤田先輩のようにもっと遺族と接したいんです。飾りの祭壇組み立てや片づけとかが嫌なんじゃなくて、藤田先輩のように担当者として、最後の集金まで全部やりたいんです」
店長は目を丸くし、首を左右に振り戸惑うような表情で言った。
「そりゃあ、ダメだな。冨安君。社員にならないと、一連の流れはやらせてあげられないんだよ」
即座に拒否された。僕は間髪を入れずに言った。
「じゃあ、社員にしてください!」
事務所中に声は響いた。その場に何人かいた社員も一斉に僕の方を向く。
「おい、おい」という呆れ顔も混じった表情で店長は言う。
「何いってんだ、冷静に考えてみろよ。おまえ、大学があるだろう。っていうかもう直ぐ入学式だろ。そっちはどうするんだ。親が反対するし、悲しむぞ!」
店長の逆説得が始まった。
「大学どうするんだ」っていうのはわかる。「せっかく大学に受かって、入学金まで納めているのに、
それを無駄にすることには親が反対するぞ」と言われているのかと思っていたらそうではなくて、「この業種につくのは親が反対するぞ」と言っていたのだ。さらに「悲しむぞ!」とまで語気を強めて言った。
店長は僕を諭すように言葉にする。
「仮にな、三百種類の業種があったとしたら、一番下から数えたほうが早いという業種なんだよ。それほど葬儀社っていうのは、社会的地位が低い商売なんだ。忌み嫌われたり、偏見の目で見られるんだよ。この仕事についていると言うだけで、世間の人がなんて言うか・・・・・そういう目に遭うんだよ」
十八歳の僕には「そういう目に遭う」というのがわからなかった。どうしても、この仕事がそれほど社会性が低く、偏見に満ちた職業だとは思えなかった。
「だけど、先輩たち、明るく楽しく誇りをもって、遺族に感謝されて、感動までされて、やりがいもってやってるじゃないですか。藤田先輩も、お客さんに褒められる、ああやって感謝されるのがこの仕事のやりがいなんだよ、って言ってますよ。僕もそうなりたいんです。先輩たちみたいに涙ながらに感謝されたいんです!ありがとう、って言われたいんです!」
熱くなっていた。想いが込み上げてきていた。
「我々はもう、転職したりいろいろあってここまできてるからな。この仕事を長いことやって、やりがいもわかっているからね。親の反対だけじゃなく、友達だってこの仕事をしていると言うと離れていくぞ。冨安君、お前はまだ十八だろ。お前はこの仕事以外にも可能性はいろいろあるだろう。あえてこの仕事を選ばなくてもいいんじゃないか。しかも、世の中は学歴社会だし、悪いことは言わないからやめたほうがいい」
店長は言葉を強めてさかんに言う。偏見にさらされることがわかっていたのだろう。僕には「親が反対するぞ」っていうのがよくわからなかった。まだ若くて世間を知らなかったこともあるが、僕が育った家庭では、おばあちゃんや両親からの、
「自分の好きなことを、やりたいと思うことを、やりなさいよ。その好きなことで世間様のお役に立って、ご飯が食べられるなら、こんな幸せことはないからね」
という口癖をいつも聞かされていたし、果樹農園をやっていた両親も大学に行くとき、「本当に大学に行ってやりたいことがあるんだったら、行きなさい。でも学校での勉強がすべてじゃないからね。学校の勉強よりも大切なことは、社会に出てからしか学べないからね」
と言うような人だったので、うちの親は反対しないのではないかという気がしていた。
世間の常識はこれとは違うと気づかされたのは、のちに長いつき合いの彼女の両親に、結婚の許可をもらいに行ったあの衝撃的な日であった。そのとき、僕は店長の言葉をありありと思い出したのである。
店長はさらに言う。
「とにかく学歴社会の時代だ。大学へ行けよ。四年間バイトで使ってやるから、それでもまだこの仕事と思っていたら、またその時は考えようや」
これでその話は終わり、と言わんばかりの口調だ。
諦めきれない僕は聞き返す。
「でもそれじゃあ、遺族と接することも感謝される場面に関わることも出来ないじゃないですか?」「分かった、そこまで言うんなら・・・・だったら冨安君!先ずは親に聞いてこいよ。どうしてもやりたいなら、とにかく、大学進学をやめて、この仕事に就いていいか親の許可をもらってきなさい」
結局僕は親の許可を取らなければ前に進めないと思った。それでも、店長の言うように、もしも親に反対されたら困るとの思いもあった。実家へは片道六時間以上掛かるので一日休んで許可してもらいました、では嘘っぽいと思い、二日間の休みをもらい、実家へ帰った振りをし、後ろめたかったが親の許可を取ってきたと嘘をついた。うちの親は反対しないだろうとは思ったが、あれだけ店長に言われると、もしかしたら反対されそうな気もしてきていたのであった。
そして翌日。
「親はそんなにその仕事が気にいったのなら構わないと言いました。好きなようにしなさいと言ってくれました」
キッパリと躊躇いもなく嘘を言い切った。
「ええっ~? ほんとかよ!」
店長は想像を超えてびっくりし、目を丸く見開き言った。
「せっかく大学入ると思って、入学金はもう納めてもらったんだろう」
「仕方ないです。この仕事で働いて返します」
僕はかっこつけて言うが、更なる障壁が行く手を遮る。
「他にもう一つ問題がある。この仕事は年齢が必要なんだ。うちで一番若い藤田が四十を越えているんだぞ。その若さじゃあ信用されないからダメだな。分かるか。君が相手にするお客様は、両親以上の年配の方達なんだからな」
「店長、それはないじゃないですか! 親の許可が取れたらいいって言ったじゃないですか」
店長も「それは逃げ口上だった」と言えなくなって、ともかくアルバイトとして続けることになった。入学式の日はとうとう大学に行かず、僕は毎日のように葬儀社へアルバイトに出かけていた。とにかく僕はこの仕事から離れたくなく、大学は辞退し、葬儀社への道を選び働きはじめた。
社員になる許可はもらえなかったが、親には「いいアルバイトが見つかったから仕送りは要らない」と言ってしまった。アルバイトの給料は一ヵ月後に入るので、その間はカップ麺で食いつなぐ。二十個入りの大箱を買い込んであって、食べるのはそれだけ。朝、会社へ行くと藤田さんに「朝飯食ったか?」と聞かれ、「まだです」と答えると、喫茶店でモーニングセットを食べさせてくれる。そのあと昼飯も食べさせてくれて、夜は夜で、「俺んちに遊びに来い」と誘われ、奥さんの温かく美味しい手料理をご馳走になる。給料日までの一ヵ月間、指導社員というより親代わりみたいに面倒を見てくれた藤田さん夫婦であった。
藤田さんは歌が好きで、僕がシンガーソングライターを目指していて結構上手く歌えることを知ると、8トラ(8トラック・カートリッジテープ。録音用の磁気テープのこと。当時のカラオケはこれだった)のカラオケスナックにつき合わせては、「フォークソングも良いが、演歌か、せめて歌謡曲を覚えて歌え」なんて言う。初めて演歌や歌謡曲を覚え、歌ったのも、飲みにいくことを覚えたのもこのときである。僕は下戸でお酒はまるっきりダメだった。もっともまだ未成年なので藤田さんも無理には勧めてこなかった。
アルバイト期間は後に思えば短い期間なのだが、社員にさせてもらえない歯がゆさがその時間を長く感じさせ、感情的にさせていた。
「店長! 早く社員にしてください!」
と懇願するたびに、
「若すぎるからなあ。一番若い社員の藤田が四十一歳だからねえ」
はぐらかせるような口調で幾度となく言われた。
*
アルバイトしながら、諦めの悪い僕は店長に「社員にしてください、社員にしてください」と言い続けていた。一方で、藤田さんにも自分の覚悟の気持ちを打ち明けて頼んだ。
「もう大学行くことも辞退して、後を絶っています。この仕事で、藤田先輩みたいになりたいんです。そこまで覚悟してるんです。でも、会社がダメだって言うんです。若いからダメだって。先輩からも店長に言ってくれませんか。お願いします!」言ってはくれたが、年齢が十代ではやはり信用されないからダメだと、藤田さんも店長に言われてしまう。
「社員になれるかなれないかじゃなく、どうしてもなりたいんです。ですから、そのときに備えて飾りつけと片づけだけでなく、遺体の扱い方も物品の名称も司会も各宗派のことも全部教えてください!」
僕はもっとこの仕事を知りたくて、やりたくて、先輩のように感謝される担当者を目指したくてたまらなかった。
「おまえそこまで本気なのかよ?」
「本気です。いつ社員になってもいいような自分になって、店長にそのぐらいの覚悟の気持ちがあることを示したいんです」
藤田先輩は真顔になって僕をジッと見つめた後、
「わかった。おまえがそこまで考えているのなら協力してやるよ」
それからは、仕事中、飾りつけと片づけだけではなく、藤田さんは何時間か自分の仕事に僕をつき添わせてくれるようになった。これまではアルバイトとして、藤田先輩のすることを遠くから見ているだけだったが、今やすぐそばで先輩の言うこと、することを見ることができた。一挙手一投足を食い入るように見て、メモを取りまくった。人は目標(この時の僕は「先輩のような社員になること」)
が出来ると集中力は半端ないとリアルに感じていた。学校の勉強とは違う学びには、ものすごい高揚感があった。
藤田さんが司会をするときは、式の一時間前に会場に行って待ち構えて聞いた。宗旨に合わせた祭壇まわりから受付の配置、式全体の導線チェック。お寺様との進行の打ち合わせ、その他、遺体の処置、安置など、宗旨の違いによる施行(葬儀の実施、進行)のすべてを覚えていった。そのころはマニュアルがなく、手書きでメモを取り、その後に整理しながら、まとめ上げて覚えていったので、僕なりの葬儀マニュアルが膨大なノートに溜まっていった。
ある日、藤田先輩について病院の霊安室へ遺体を受け取りに行った。アルバイトをそんなところへ連れていくことは基本ないのだが、社員を前提とした教育を、内緒で藤田先輩が実施してくれたのである。多分、店長はその事に気付いていたと思うが、見て見ぬ振りをしてくれていた。霊安室の祭壇周りを整えて先輩と待っていると、間もなく廊下を遺体を乗せたストレッチャーとともに人々がやってきた。霊安室は医師、看護師さんたち、それに遺族の人たちでたちまちいっぱいになった。お顔の白布を取り、お焼香を始める。この仕事を始めて、じつは遺体を間近に見るのははじめてだった。故
人はまだ六十代くらいの女性で、息を引き取って時間がたっていないから顔色は変わっていないけれども、表情がないので蝋人形のような印象を受けた。忌み嫌うような嫌悪感は、僕にはなかった。
家族のすすり泣きが起こり、やがてオイオイと泣きはじめた。そうなるとおばあちゃんっ子だった僕は、大好きなおばあちゃんを思い出してもらい泣きをしてしまう。感情移入をしやすい僕は、どうもおばあちゃんのケースになると、ご家族と一緒に泣いてしまう。自分でもどうしようもない。感情のコントロールが出来ない。「この仕事に向いていないのではないか」と一瞬不安になった。