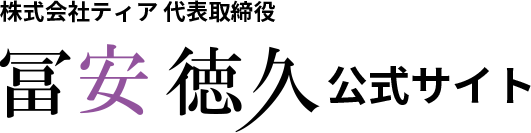願えば叶う ~十八歳の決意~
第1章 十八歳で"天職"に出会う 4
初夏の風が吹き渡り、一の坂川沿いの桜葉が柔らかな若草色に色づいた五月の終わり頃、藤田先輩が店長をまた口説いてくれた。
「店長、冨安君こんなに勉強してるんですけど、なんとか社員にしてやってもらえないだろうか。入学式すら行かず、大学への進学はやめたみたいですよ」
しかし、会社の方針として、やはりこの仕事は年齢が必要とされる。「年齢=信頼」の仕事。十代の担当者では信用されないからダメだと言われる。それでも藤田さんは「あいつの覚悟は半端ないですよ」と、本気で店長を口説いてくれている。僕も機会を見つけては、
「こんなに仕事(メモノートを見せながら)を覚えました。お願いします。社員にしてください!」
と店長に熱く言い続けていた。親から頂いた性格なのか、とことん諦めない自分がいた。
この会社には!毎月定例の会議がある。六月の初旬、店長会議が下関の本社で行われ、店長もそれに出席した。店長会議が終わった後、各店長は社長に挨拶がてら声を掛けて言葉を交わす。そのとき、店長は僕の話を切り出してくれた。
「社長ちょっとお話があります。うちに今十八歳なんですけど、入る予定の大学にも行かずうちでアルバイトとして働いている子が、社員になりたい、社員になりたいと言ってるんです」
「十八歳? そんな年齢じゃ若過ぎるからダメだろう。どこかの葬儀屋の息子か?」
「いえ、葬儀屋の息子ではないんです」
「なんで、十八歳の若さで社員になってまで葬儀の仕事をやりたいんだ?」
「うちの藤田という社員の後姿を見て感動したらしく、どうしてもやりたいと言い出したんです」
少し考えた後、社長は言う。
「変わったやつだな。そんな変わったやつなら、ちょっと会って話してみたいな」
ここから奇跡の歯車が回り出した。
「ほんとですか? 会うだけ、面接だけでもしてやって下さい!」
高揚した口調で頭を深く下げてくれたそうだ。翌日、店長から呼ばれ、社長面接の話を聞いた時、驚きと共に、とうとうそのときが来たと思うとすごく嬉しかった。日程を決めて頂き、僕は下関の本社まで行くことになった。この指示に心底驚いたが、同時に、チャンスをもらえたので思いっ切り、覚悟の想いを伝えて来よう、と決意を新たにした。強く願えば、叶う。その入り口が見えた。
下関は、歴史の交差路である。旧くは永い戦乱で疲弊した京都に対して、西の京都といわれた長州は貿易港である。関門海峡を挟んで北九州と中国地方を支配して、明との貿易で豊かな富を蓄積した大内氏が、大内文化を花開かせた地であった。
幕末においては、関門海峡を通る四ヵ国艦隊に、長州藩が攘夷を実行して砲撃を加え、反撃を浴びて下関砲台を叩き潰されたことで知られている。関門海峡を見下ろす丘にある日和山公園には、坂本龍馬の次に僕の好きな高杉晋作の陶像が立っている。
もちろん社長とは初対面。社長室の前で立ち止まり深く深呼吸した。直立不動、緊張感はピーク。意を決して、ドアノックをし「失礼します」とかん高く声を発した。背はそれほど高くないが、肩幅が広く胸板の厚い体型は、僕の勝手なイメージからすると柔道家のような感じだった。
「葬祭事業部山口店でアルバイトをしています冨安です。店長から指示を受けて面接に参りました」
震える心を抑えて伝えた。応接セットに座るように促されると、雑談もなくいきなり聞かれた。
「冨安君と言ったな。君はどうして葬儀の仕事をしたいんだ?聞くところによると、葬儀屋の息子でもなんでもないんだろう?」
「はい、大学に入るために、こちらに来ただけです。入学式前、偶然アルバイトで山口の支店にお世話になって・・・」
「アルバイトじゃなくて社員になってまで、どうしてこんな葬儀の仕事がしたいんだ?ましてや大学やめてまで社員になりたいと言っているらしいが」
「はい、そこで、指導して頂いている時、藤田と言う先輩がご遺族に感謝されている姿を見まして。いや、あんなにご遺族の方に、涙ながらに感謝されている先輩社員に感動したんです。それを見て、僕もあんな風に心から感謝されたいと思ったんです。いつか将来は心から感謝される仕事に就けたら、とずっと思っていたんです」
緊張しながらも、一気に伝えた。熱く伝えた。真実の想いだから嘘はない。
社長はジッと僕を見つめていた。次の瞬間、
「……わかった。大学に行かなかったこと後悔しないか?」
「しません! 大学に行く目的は特になく、大学での四年間は、将来、世の中に役立つために何かすることを見つけるためだけですから」
間髪入れずに答えた。一瞬、大学四年間で歌をやり、チャンスを待とうとしていたことが脳裏をかすめるが、これまで数々のオーディションを受けてみて、上には上がいることを実感していた。そのことが胸のどこかにはあったのだろう。歌で感動を届ける以上の感動がこの仕事なら届けられる。そう思った僕の心に迷いはなかった。
社長は軽く頷くと、四角い顔が満面の笑顔に変わった。
「冨安君・・・・といったかな。なるほどね。熱意は伝わったよ。本気なんだな、君は。店長には私から採用だと言っておくが・・・・・・ただな、年齢がいってないことによって、信用されないことがあるからな。それと・・・・そういう目で見られるから、それだけは承知のうえで覚悟してやりなさい」
と言いながら、握手のために差し出された手を僕は両手で掴み、
「ありがとうございます!!」
叫ぶように伝え、深々と頭を下げた。分厚い手でぎゅっと握りしめられた時、社長の手から期待されている温かさが伝わってきていた。ただ、社長が最後に言った「そういう目」の言葉が少し気になった。
晴れて、念願だった葬儀社の社員になった。十八歳の夏、葬儀ビジネスへの本格的な一歩を踏み出した。僕の運命は大きく動き出したのだ。