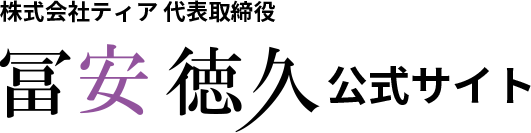若さが障害に ~担当を替えてくれ!~
第2章 遺族の悲しみに寄り添う
晴れて社員になったからには、一日も早く司会がしたい。葬儀の担当者として、遺族にもっと「ありがとう」と感謝をされたい。先輩社員の司会を務める姿を見ては、「かっこいい」と思った。ライブをやって人前で歌ったり、しゃべったりすることに慣れていたことが、司会に惹かれた理由かもしれない。
しかし、葬儀、告別式の司会は、あくまでも黒子であり、そして、単なる進行係ではない。司会の善し悪しで式全体の出来、不出来が決まってしまうくらい責任の重いものだ。そのことをどれだけ理解できていたか怪しいものだったが、その目標に向かって無我夢中だった。休みを取ることさえ忘れていた。目標があったから「やらされ感は0(ゼロ)」の自分がいた。肉体的にはつらい時もあったが、心はまったくつらくない。
打ち合わせや集金に行く藤田先輩について歩き、一つ一つメモを取り、それを書き直して覚え込んでいった。僕にも絶対にやれるという自分への期待が自信を引き寄せていった。そして、満を持して店長に申し込んだ。
「店長、そろそろ司会までやりたいと思っています。僕の司会の演習を、ぜひ見てくれませんか?」
それまで、自分から司会をやらせてくれと言った新入社員はいないらしい。
「あいかわらず、熱心だなあ。それじゃあ、支店内の定例会議のときに時間を作ってやるよ」「はいっ!ありがとうございます」
第一友引前に毎月開かれていた定例会議の終わり頃に店長が切り出した。
「今日は、富安君が司会の演習をみんなに見てもらいたいということで、皆さんの時間をいただきたいと思います。冨安君、ここで模擬葬儀司会をやって見せなさい」
「ありがとうございます。それではふつつかながらやらせていただきます」
僕の模擬葬儀の司会は、みんなから褒められる中の合格だった。だが、目標は司会だけではない。一つの葬儀を丸ごと担当して自ら采配をふるい、最後の最期に遺族から「いい式でした。ありがとう、富安さん」と言われることだ。アルバイト時代から藤田先輩についてまわり、一連の流れを最後までできる自信があった。
「じつはですね、できれば司会だけではなく、打ち合わせから通夜から葬儀の段取り、施行もすべて担当させていただきたいのです。ちょっと見ていただきたいのですが、いいでしょうか?」
模擬葬儀の司会に続いて、先輩を相手にロールプレーイング(先輩社員を喪主に見立てての葬儀の打ち合わせの実地演技)を実演して見せた。
「おいおい、いったい、いつの間にそんなに覚えたんだ」
その言葉と先輩社員たちの驚きの表情が、僕には最高に心地良かった。
*
更に藤田先輩からマンツーマンでの研修を受けて、いよいよ一担当者としてメインで取り仕切ることを考えているとワクワクして高鳴る気持ちを抑えきれない。そして、ついにその日はやって来た。一人でのはじめての仕事は病院からの一本の電話だった。山口市の隣、防府市の市民病院で亡くなった患者だった。いくたびも藤田先輩について歩き、教わり、克明にメモを取ってきた。自信はあるのだが、自分一人で責任を持ってやるのだと思うと胸がドキドキしてきた。今日は藤田先輩がアシストとしてついてくれているので、心配することはないはずなのだが。
このくらいの規模の病院になると、守衛室に寄って霊安室の鍵をもらわなければならない。霊安室に行き、扉を開けて藤田先輩と待っていると、病室から看護師さんたちがストレッチャーで遺体を運んできてくれた。ドクターもついている。それを受け継ぎ藤田先輩とそのままストレッチャーを押して、霊安室の祭壇の前に移動させて焼香の準備をする。まず遺族が先に焼香して、看護師さんたちも続いて焼香した。主治医かどうかわからないが、ドクターも最後に焼香していた。それが終わると、僕たちが持ってきた遺体の等身大の敷布団を敷いたストレッチャーを横に並べて遺体を移す。藤田先輩と僕以外に看護師さんたちにも手伝って頂き遺体を支え上げながら移すのである。普通のストレッチャーは台車のままで折りたためないが、こっちのストレッチャーは足が折りたためる寝台搬送車用になっているので、ガシャンと足を折りたたみながら車に入ってしまう。
そのままバンタイプの遺体搬送車に乗せてハッチバックドアを閉め、僕たちが手を合わせて一礼し、更に看護師、ドクターの方に向きかえり「丁重にお送りさせて頂きます」と伝え、深々と一礼した。車に乗り込んで振り返ると、後方に並んでドクターと看護師さんたちが頭を下げているのが見えた。
道案内のために遺族の一人にほとけ様の横の後部席に乗ってもらって、僕が運転席で藤田先輩が助手席。その車の後ろをほかのご遺族の車もついて来る。ほとけ様は山口市内にある自宅に戻ってきた。一報が入った時の電話で遺族には前もって、敷布団を敷いておいてもらうよう頼んでおいた。到着した車のドアを開いてストレッチャーを引き出すと、そのまま脚が立ち上がる。一番上が担架になっているのでそれをはずして、部屋のなかへ二人で運べるようになっている。このときは家族の男性二人が手を貸してくれて、四人で奥座敷へ運び入れた。以前は玄関から遺体を運び込んだら、出す時は縁側から、というように同じ経路を辿らないというような習わしがあったが、現状は居住環境やその間取りなどによって難しくなっている。
遺族の方にお願いしておいたように、座敷には真っ白なシーツをかけた敷布団が敷かれ、枕が置かれていた。ほとけ様の枕はシーツか敷布団の下に隠して、布団が盛り上がるようにすることになっている。枕直しは一連の動作だ。お釈迦様は枕をしていなかったからである。手早く枕を直して、北枕か(部屋の形状によっては西枕)どうかを確かめる。そして、病院から等身大の布団に包まれてやってきたほとけ様を、その布団ごと座敷の敷布団に移す。両端に持つところがあって、棺に入れるときも等身大の御遺体専用布団ごと入れるのである。季節は真夏の七月、手早くドライアイスを施す。当てるところは基本的に決まっている。腰の両側と、両脇腹。内臓のところが一番腐敗しやすく臭いが出やすい。顔の色が変わってきそうなときは、顔の横に綿花でくるんだドライアイスをきれいに整えて置く場合もある。綿花というのは、ハンカチくらいの大きさの綿である。ドライアイスは新聞紙でくるんでいるだけなので、綿花できれいにくるんで、遺体に寄り添うように置くのである。昔と違い今は空調設備が各家庭でも完備されていて冬も暖房が効いているので、一年中ドライアイスは欠かせないのだ。ほとけ様に掛け布団をかけ終わると、
「掛け布団はなるべく開けないようにしてください。なかの冷気を閉じ込めておきたいのでよろしくお願いいたします」
遺族の方に注意を与えた。ほとけ様はおばあちゃんだったが、すでに病院の看護師さんたちにつめ物も施され、髪を整えられ、薄化粧も施されていた。ナースたちも「エンゼルセット」と呼ばれる物
を持っている。セットのなかには櫛、口紅などの簡単な化粧道具、脱脂綿、ピンセットなどが入っている。それは病院で揃えてくれたわけではなく、看護師さんたちが持ち寄り用意したものを使うのである。のちに親しくなったある病院の看護師長さんが、
「これ全部、私たちが持ち寄って用意したものなの。女性なら特に最期は綺麗にしてあげたいじゃない。だから、やってあげたいときがあるから持っているのよ。本当は本人が使用していたものを使えればいいんだけど、病院まで持ってきていない人がいるので」
と言っていた。病院ではなく、自宅で亡くなった場合は、遺体の処置は僕たちがしなければならないけれど、まだ僕は一人ではそのケースに遭遇していなかった。
*
次に、枕経を唱えにお寺様がやって来る前に、枕飾りをしなくてはならない。枕経は亡くなってすぐ、枕元であげるお経で、亡くなった人はこれを唱えてはじめてほとけ様になれる。だから、深夜に亡くなった場合でも菩提寺があればすぐに連絡する。それでも時々、「明日朝、○時に行きますので」と駆けつけてくれないお寺様がいる。そんな時は少し寂しい気持ちになったのを覚えている。
ご遺族の家に到着した直後に、お寺様に電話をした。菩提寺が確認出来ていたので、着くなり直ぐに一方入れた。お寺様にも都合や準備があるので、できるだけ早い連絡は必須だ。
これから枕元を整え、心静かにお寺様を迎えることになる。仏壇の前にお経を読む小さな経机というものが大概の家にはあるが、もしもの時も考えて、それの代用品を常に持参している。そうやって枕飾りを整えるのである。宗旨にもよるが、この地域で最も多い禅宗、真言宗などでは、その上に載せるものは次のように決まっている。
まず、花瓶にお悩を一輪挿しにしたもの。お悩という植物は一年中緑の葉で、清めの意味がある。辞書によれば、「仏前に供え、木の枝のほうは数珠などにする」とある。それから、蝋燭立て。その二つの手前の中央のところに香炉。それらが逆三角形の形で、経机の上に置かれる。お線香を出し蝋燭に火をつける為のマッチ箱とお鈴(仏具の一つ)を置けば、枕飾りの準備が整う。後は枕経をあげてくれるお寺様の到着を、遺族と一緒に待つのであった。
枕経が終わると、お寺様の都合を最優先に、通夜や葬儀の時間を決め、火葬場の窯の時間が取かを確認する。戒名を書く白木の位牌は「翌日、お寺にお届け致します」と伝える。そのお寺様はいったん帰って、また通夜のときに戒名を授けた白木の位牌を持参して来る。それを受け取り、祭壇中央の位牌台に置き通夜の勤行をする。翌日の葬儀と火葬場、それから初七日での勤行まで、一連のセットになっているのだ。
もっとも重要な打ち合わせは、お寺様との時間の調整である。式の時間が決まらないと、事が進まない。関係者への訃報連絡も出来ない。お寺様との間で「何時から何時でよろしいでしょうか」「何月何日、何時から何時で法事があるから午後からにしてくれ」というやり取りが必ずある。タイムリーに枕経に来てくれないときは、「焼き場(火葬場)お時間だけ押さえたいんですけど」と、電話で緊迫したやり取りになることもある。
すべての流れの締めくくりは、火葬場の窯の時間を押さえることである。火葬場の運営は、今ではその多くが市役所などの自治体なので、その窓口に申し込むのである。何時から何時とお願いして「その時間はふさがっています」と言われると、またお寺様に連絡して「それでは一時間ずらしてください」とお寺様に言われて、調整になるのだ。火葬場の窯の受付が一時間きざみなので、社葬や会葬者が特別に多い葬儀以外は、葬儀・告別式はほとんどが一時間きざみになるのである。
*
「担当責任者としていくつかの葬儀関わり始めていた頃に試練は来た。この仕事で、思いがけないことが起こったのはこのときであった。下関の本社で社長に面接されたときに、「年齢がいってないことによって、信用されないことがあるからな。そういう目で見られるから、それだけは承知のうえで覚悟してやりなさい」と、すでに予告されていたことだった。
少し慣れ始めていた頃に担当したある葬儀。お通夜前に白木の位牌を持って、葬儀全体のスケジュールを決めるために、菩提寺が家から近かったこともあり、すぐさまお寺様に駆けつけた。枕経のときは遺族だけで行われたので、お寺様とはまだご挨拶もしていなかった。僕は名刺を差し出して、
「窪田家のお式ではお世話になります。担当の冨安と申します。よろしくお願いいたします」
と伝えると、怪訝な顔をしながら、
「えっ!おまえがやるのか?若いなぁ・・・だいじょうぶか?ちょっと早すぎるのやないか」
「十分研修もして頂き少しですが経験も積みました。ご心配いりません。大丈夫です。きちんと担当させて頂きますからお任せください」
いくら説明しても、打ち合わせに入るどころか、会社に電話をかけはじめた。
「あんたのところ、何を考えてるのか?あんな若い子に担当させて!」
通夜が迫っているというのに、こんなことしている場合か、とやきもきしていると、電話の会話は、
「担当者を替えるわけにはいかんのか?」と、ますます危ない方向へ話が傾いている。電話を受けた店長が、粘り強く説得を続けてくれていたようだ。やっとのことでお寺様がしぶしぶと打ち合わせに応じてくれたときには、訪問して一時間近くたっていた。はじめて担当した仕事は病院からのもので、比較的楽かと思われたが、集金が終わる最後まで、ハラハラドキドキであった。緊張感が緩むことはなかった。
その後の仕事でも、社長から懸念されていた若さゆえの試練は幾度となく味わった。それは、お寺様からは見兼ねるほど、担当者が余りにも若過ぎる不安。そして、打ち合わせをする喪主は僕の親よりも年が上である事。が故に、ご遺族から見た若過ぎる担当者への不安。
「君が?本当に君が担当するのか?」
いぶかしそうな顔で言われることは何度もあった。心配して会社に問い合わせがいくこともあった。そのたびに店長や藤田先輩が、
「あの子は若いけどしっかり教育されています。経験も積んでおりますから、ご心配いりません。本当に一所懸命やる社員ですから間違いないです」
と力強くフォローしてくれた。
僕は情けなくて、悔しかった。でも、なんといっても自分がやりたくて始めたことだ。お寺様や喪主がどんなに不安そうな顔を見せても、動じる様子を見せてはならないと自分に言い聞かせ、通夜から葬儀まできちんとお世話させていただこうという気持ちでいっぱいだった。若いという現実は仕方なく、とにかく一所懸命さを出し切ること。それが今の自分のできる精一杯のことだと思った。とは言え、まだ十代の若者に先輩社員のような落ち着きと貫禄が見られるわけもなく、菩提寺や遺族、親族には頼りなく見えたに違いない。少しでも年が上に見られるように、コンタクトレンズをやめ、黒ぶちの眼鏡に替えてみたりもした。この頃は、本当に早く年を取りたいと心から思っていた。二度目の担当のときも、喪主との打ち合わせを済ませたあとお寺様へ行き、ご住職との打ち合わせから、あらゆる手配や段取り、準備を終えたときも、まだ喪主の不安そうな表情が消えない。
通夜が無事に終わり、翌日の葬儀、告別式も滞りなく終了する頃には、喪主の表情が和らぎ、僕にはときおり感謝の微笑みさえ見せてくれた。そして最後の集金のときに、
「ありがとう。君のおかげでいい葬式ができたよ。しかし、本当に富安さんは、若いのに一生懸命尽くしてくれるんだね」
最期の場面に関わった僕に心からのありがとうを言ってくれた喪主の顔がとても嬉しそうで、僕も、「この仕事を選んでよかった、一生の仕事に巡り会えた」という気持ちになっていた。
初仕事をした頃の必死な気持ちとあの遺族の方々の安堵感が感じられる情景は一生忘れることはない。最期のありがとうを頂ける何ものにも代え難い幸せ感を、僕は経験を重ねる度に味わっていた。そこには、お金以外の大切な報酬「やりがいと生きがい」という報酬が溢れていた。