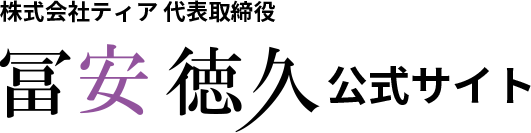破談 ~最低の仕事~
第1章 十八歳で"天職"に出会う 1
一九八一年の秋の深まりが感じられる頃、当時二十一歳の僕は、高校時代から付き合っていた彼女の家を訪れた。今夜は彼女の家族と一緒に食事をすることになっていたのだ。高校時代から幾度となく出入りしていた彼女の家だが、これから行動することへの緊張からか、初めて訪れた時のような落ち着かない気分だ。気候は良い季節だというのに、手に脇に汗をかき始めているのがはっきり分かった。
大きなテーブルを囲んでの夕食。僕を歓迎してくれているのが分かる豪華な料理が所狭しと並んでいた。他愛もない食事をしながらの会話が進むと僕の緊張感はほぐれていった。僕は食事をしながらも、タイミングを探っていた。これまで幾度となく出入りし、彼女の父親とも会っていた。長女である楓の事がことの外かわいい存在であることは感じていた。
話を切り出すタイミングが訪れ、僕の緊張はピークに達しようとしていた。僕は彼女のお父さんの前で改まって両手をつき、切り出した。
「お父さん、楓さんと僕は同じ高校で、楓さんが十六歳のときから真剣におつき合いをさせていただきました。仕事もこちらへ戻ってきて落ち着きましたので、結婚をさせていただきたいと思い、改めてお願いに参りました。必ず楓さんを幸せにしますので結婚させて下さい!」
二十一歳の若さではあるが、僕の仕事は順調で、はるかに年上の先輩と同等の仕事をこなし、給料も上がって自立していく自信があった。そして、結婚しても十分にやっていける自信もあった。高二のときからずっとつき合っている彼女も、今は短大を卒業していた。そこで、ご両親にご挨拶しに来たのである。
この家は、代々続く畳職人の大家族で、食事は広い居間にある長い食卓で、おばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、お母さん、兄妹たちが決まった席について食事をする。筆頭、上座に座るひいおばあちゃんも九十歳を超えているがピンピンしている。
ひいおばあちゃんは僕が若いにもかかわらず、いつも正座をして、長い正座の後もスッと立ち上がって歩くので、「若いのに大したもんだ」と感心して、ひいきにしてくれていた。
じつは、前の会社の研修に正座があったのである。三十分間正座してサッと立てなかったら、もう一度研修をやり直さなければならない。指導係の先輩から、足の親指の組み替えでしびれを逃がすなどコツがあると教えられていた。仕事柄、マナーや作法に関しては厳しく指導されていた。ひいおばあちゃんのみならず、両祖父母もご両親も僕のことは「若いのに礼儀正しい。素直でなかなかいい子だね」と言ってくれていたらしい。
「いつかそういうときがくると思っていたよ」
そう言うお父さんの顔は、包み込むように優しく笑っていた。
「楓ちゃんの気持ちが一番なんだから、楓ちゃんが良いなら、いいんじゃない」
と誰かの声が聞こえて、
「結納はきちんとしなければならないね」
「向こうの(僕の)両親へのご挨拶はいつ頃にしようか?」
親子代々職人で格式を重んじる一家は、僕と彼女を交えて、いつの間にかさまざまな段取りの話になっていた。僕は大きな山を超えた気分で、緊張感が薄れていくのを心地よく感じていた。次の瞬間だった。
「ところで、今の会社であんた何をやってるの?」
ひいおばあちゃんが突然聞いた。僕の勤めている会社は『皇諒閣(こうりょうかく)』名前からして結婚式関連の仕事だと思っていたのだろう。僕は何のためらいもなく、いや、むしろ自慢げに答えた。
「葬儀の仕事をさせて頂いてます。すっごく人に感謝される仕事なんですよ。大切な方をお送りする最期の場面で人のお世話をするというのは本当にやりがいもあり、感謝される仕事なんです」
この仕事を僕がどんなに好きで、やりがいを持ってやっているか、彼女がある程度話してくれていると思っていた僕は、胸を張ってニコニコしながら話し続けていると、おばあちゃん、おじいちゃんそして両親の顔色が変わっていくのがはっきりとわかった。次第に笑顔は消えていった。
異様な場の雰囲気を気にして、いつも明るい妹さんが話を替えさせようと、目配せをしているのが目に入る。そのとき、ひいおばあちゃんが口を開いた。
「あんた、がんやか?」
言っている意味がわからなかったけれど、突然日がかげったような暗い目の奥が不気味だった。
「がんやって・・・、なんですかね?」
「葬儀屋のことだ!」
もう一人のおばあちゃんが、これまで見たこともないつっけんどんな言い方で答えた。棺桶を用意する人、つまりは葬儀屋を、昔からこう呼んでいたらしい。普通の職業につけないような人がする仕事という感覚だろうか。
「君はそんなことやってるのか。結婚式のほうじゃなかったのか?」
と今度はお父さんがいぶかしげに言う。
僕は小さくかぶりを振って
「はい、僕はずっと山口にいた時からこの仕事をやっています」
そして彼女のほうを見た。声にならない声で口を動かした。
(「言ってないの!?」)
(「ちょっと来て!」)
彼女に腕を取られながら、二人で席をはずし、となりの部屋に行った。
「冠婚葬祭の会社っていうのは言ってあったけど、そういう仕事とは言ってなかったの。ここまで表情変えるとは思わなかったわ」
「完全にみんなの顔色が変わったよね。でも、この仕事、僕は誇りをもってやっているし、どれだけ大切な仕事か、そのことをちゃんと伝えるよ、大丈夫、納得してもらうから」
「….うん、そうして」
彼女は不安な気持ちを振り払いながら言った。席に戻ってもう一度話をしようとしたら、
「今日はもう帰ってくれ」
とお父さんに言われ、荷物を持たされ、玄関まで追い出されるように送られた。「ちょっとお父さん、僕の話を聞いて下さい!」
取り付く島もなく玄関へ追いやられた。
「とにかく、今の部署から替わったら来い。その仕事だけは絶対にだめだ! 娘の婿が葬儀屋なんて、親戚にも近所にも顔向け出来ない」
玄関で立ち尽くす僕は、この状況を受け止められずにいた。お父さんの背中越しに見える彼女の顔は僕以上に戸惑っていた。
ところで僕は、『竜馬がゆく』(司馬遼太郎著)を読破した中学三年のその時から、坂本龍馬の大ファンになった。高一の夏休みにはアルバイトでお金を貯めて、土佐の高知・桂浜までたった一人で坂本龍馬(銅像)に会いにいったほどの、龍馬ファンとなっていた。先生から強く薦められて、とにかく今読めと言われ読破したおかげで、僕の中で生き方を刺激する何か大きなスイッチがはいったのだ。
龍馬の愛した女性は”おりょう”という名であった。龍馬が幕吏に襲われて重傷を負ったとき、彼女は裸同然の格好で薩摩藩邸まで助けを呼びに走ったという。僕は自分の彼女のことをいつも「おりょうさん、おりょうさん」と呼んでいた。葬儀の世界に飛び込んでから彼女には「龍馬さんのように、僕にもやるべき使命が見つかったんだ」と会う度にこの仕事のことを話していた。
*
この仕事に対する彼女の家族からの偏見でひるんではいられない。僕はまた彼女の家を訪ねていった。玄関を入ると上がりがまちに広い土間がある。土間と座敷の間に、土間より少し高くなっている広いフローリングの床がある。そこに畳を載せて作業をする台が何台か置かれている。ここに入ると、真新しいイグサの臭いがする。僕はこの臭いが好きだったが、今はその臭いさえも鼻の奥を刺激して辛いものだった。フローリングの床に正座をして土下座をし、
「お嬢さんを必ず幸せにしますから、この仕事だけは続けさせて下さい!」
と懇願したが、
「そんな最低の仕事をしているやつが・・・・棺桶屋が娘の婿じゃ、親戚にも顔向けできん!とにかく、頼むからほかの部署に移ってくれ。結婚式の方じゃダメなのか?」
何度懇願しても返ってくる言葉はこれであった。今のように携帯電話もない時代だから、彼女との連絡もままならない。電話をかけてお母さんが出ると、いきなり「仕事替わった?替わるまで電話をかけないで!」とキツく言われる。たまに妹が出たとき、友達からかかってきた振りをしてつないでもらうことができた。
こんな状態が一ヵ月も二ヵ月も続いたある夜、車のなかで彼女と話し合いになった。「私とほんとに結婚したい?」
「もちろん、そうしたいよ。決まっているじゃないか」
と答えると、彼女は訴える目で言った。
「本当に結婚したいって思っているのだったら、お願い、部署を替えて」
「ちょっと待ってくれよ。僕がどれだけこの仕事が好きか、やりがいもってやってるのか、楓、お前が一番分かっているじゃないか!」
そして、意を決し伝えた。
「楓、家を出てこいよ。結婚したらどうせ家を出るんだから、同じことじゃないか」
沈黙が重たい。その少しの間が、僕に彼女の無言の答えを伝えていた。
「それは…無理かも…」
「家族には逆らえないってことか・・・・」
「ねえ、私が大切なら、本当に結婚したいなら、お願いだから仕事替わって…」
涙声で震えながら訴える。どれだけ話しても最後の答えはそれだった。
その後、彼女から電話がかかってこなくなった。数日後電話をすると母親が出た。
「冨安君、あなた、どこから電話しているの?」
明らかに刺々しい口調だ。
「近くの公衆電話からです」
「うちから三つ向こうの筋に喫茶店があるでしょう。確かビードロっていう喫茶店。そこで待っていて」
この店は、高校時代からよく彼女と待ち合わせをしたところだ。待っていると、お母さんがあわただしく現れた。
「あなたね、楓を幸せにしたいのだったら家族の理解を得なきゃダメでしょう。そんな最低な仕事、替わればいいじゃない、同じ冠婚葬祭なんだから。そんな世間体の悪い仕事に何でこだわるの?人の死で儲けるようなそんな仕事なんてやめてちょうだい。もっとましな仕事はいくらでもあるし、そんなことで意地張って楓と結婚できなくてもいいの?」
「それは困りますけど・・・・でも仕事を替わることはできません。大切な仕事なんです。すごく感謝される仕事なんです。わかってください、お母さん!」
僕は必死だった。そして、本当にそう思っていた。
「分かったわ、ここまで頼んでも替わる気がないなら、仕方がないわね。それじゃあ、とにかく楓とは別れてちょうだい。これは、私たち家族だけの思いじゃないの。あなたが仕事を替わる気がないというのなら、これっきりにしたいって本人もそう言っているの」
あれほど僕の気持ちや僕のするこの仕事のことを認めてくれて、どんなときでもついてきてくれると思っていたが、「本人も」の言葉に、僕は打ちひしがれていた。ずっと傍にいた、いや、心だけは通じ合っていた、一番の理解者だと思っていたこの五年の歳月はなんだったのだろう。
そして、なぜこんなにも「葬儀屋」の仕事が、蔑まれ、忌み嫌われ、社会性低く言われなければいけないのだろう。悔しかった。情けなかった。そして、胸の中ではどうしようもない怒りに包まれていた。おりょうさんを失った僕は、全身から力が抜けていった。