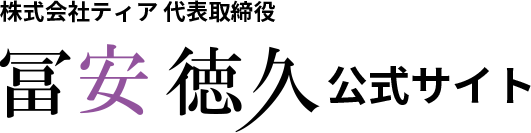運命を変えてくれた人 ~本能に目覚めた瞬間~
第1章 十八歳で"天職"に出会う 2
マスターはすぐに、バイトを紹介する約束を取ると、僕に面接時間と場所を書いたメモを渡してきた。そこには、やはり会社名は書かれていなかった。翌朝教えられた住所を僕は訪ねていった。その住所に当たる場所は二メートル超えるくらいの高さの灰色のブロック塀が道路沿いに連なっていて、なかは道路からは見えなかった。脇道に入った側にある門を入り、右側の倉庫に沿って入って行くと、倉庫の大きな出入り口の近くには、幌つきの二トン車とライトバンが六、七台並んでいた。車のサイドには〈西日本セレモニー〉と記されていた。
(セレモニーってなんだろう?)
倉庫の入り口は、トラックも出入りできるくらいの大きさなので、なかがよく見えた。ゆっくり通り過ぎながら、「何か見なれないものがあるな」と思った。一瞬、何か分からなかったが、観音開きの小窓がある。よく見ると立て掛けられたお棺が並んでいる。大好きなおばあちゃんが亡くなったときに、一度葬式を見ただけの僕でも、それがお棺だとはっきりわかったわけではないが、「何か見慣れないようなものが並んでいる」という印象だった。作業をしている人がいたが、その奥にもお棺が立てかけられて、ズラーッと並んでいるのが目に入った。生まれてはじめて見る光景だった。
「いやいや並んでる、お棺が並んでる。葬儀屋なんだ!」
お棺というものは、おばあちゃんのお葬式のときもそうだったが、つねに横になっているものというイメージがあったので、立てかけられたお棺の列はなんともいえない異様な光景に見えた。倉庫を通り過ぎるとその横手に、キンキラキンの龍が舞うかの如く仰々しい屋根の霊柩車(れいきゅうしゃ)が二、三台停まっていた。そこまで来ると左側に事務所があった。九時と約束してあったので、事務所の薄いドアをノックした。なかに入ると、元気のいい声、朝の準備をしている活気ある声が飛び交っている。
「○○家は街中だから、駐車場の確保したか~・・・」
「△△家の喪家は受付が三ヵ所必要です。テントは二間×三間を二張り……」
入ってきた僕を見て、なかの事務員さんたちも「こんにちはー」と挨拶してくれるし、「葬儀屋なのに明るい活気ある会社だな」と思った。今通ってきた、右手に見えた倉庫の光景とあまりに違う雰囲気に驚いた。事務所に入るとカウンターがあり、その前に立って見まわしていると、女子社員が応対に出てきた。
「いらっしゃいませ。今日は何のご用件でしょうか?」
「冨安といいます。面接に来ました。店長をお願いします」
「え、あなたが?」
こんな若い子が、アルバイトの面接に来るなんて思ってなかったというように、目を丸くした。狭い応接室みたいなところに通されて、店長が会ってくれた。四十代半ばくらいでキッチリと整えられた髪型、清潔感ある身なり、こんな若造の僕に対しても敬意ある応対は好印象だ。そこで、店長と喫茶店のマスターが友人だったということをはじめて知った。面接時の一通りの確認のような質問がなされた。雑談を交えた話しが途切れると、
「こういう仕事ですが、大丈夫ですか?」
店長が確認するかのように聞いてきた。
「葬儀社の仕事ですよね、僕のような学生アルバイトでもいいんでしょうか?」
「そうそう、うちは葬儀社でね、こちらは是非お願いしたいのですが、大丈夫ですか?」
また、躊躇い気味に確認するような問い掛けだ。大丈夫も何もバイトで来ているのだから、「仕事内容を教えてもらえばそれでいいんじゃないか」と思いながら、「はい」と答えると、やっと詳しいバイト内容の説明に入ってくれた。
「人夫(作業だけやる人=業界用語)的な仕事をしてもらいます。請け負った内容の祭壇などを社員と一緒に自宅とか集会所とかお寺に運び、祭壇を組み立ててもらって、それをまた片づける、という仕事をやってもらうので、とくに難しい知識はいりません」
葬儀の仕事にさして偏見がなかった僕は即答で働きたい旨を伝えた。
「どうしますか? 今日、仕事入っているから、今日からやれるのかな?」
「わかりました。今日からお願いします」
高額の時間給の魅力もあったので、間髪入れずに答えた。胸に会社の名前が入ったベージュ色のジャンパーを渡されて、名札にはとりあえず手書きで名前を書いてつけた。すると早速、社員の一人を店長が呼び、
「今日からアルバイトに来た富安君だ、藤田君頼むよ。一から教えてやってくれ」
そこではじめて僕にとって運命の人、藤田さんに出会ったのである。藤田さんは僕をしげしげと見て、
「若いなぁ。いくつっちゃ?」
驚いた表情をしながら聞いてきた。バイトって普通は若い人がするんじゃないか。どうしてそんなに若いアルバイトが珍しいのだろうと不思議だった。
「ランプのマスターの紹介だからね。やりたい夢はほかにあるみたいだけど、入学式までの三週間だし、藤田君、頼むな」
店長にはシンガーソングライターへの夢も雑談の中で話していた。
「かしこまりました」
藤田さんは四十一歳、年齢を聞いて驚いた。年齢よりも五歳以上、いや、もっと若く見えた。それでも僕から見ると十分おじさんだが、髪は短めなので若々しい感じだ。ほどよく日に焼けていて、笑うとのぞく白い歯と目尻のシワがとても印象的だ。キビキビした動きとハッキリした物言いのでかい声が、体育会系の雰囲気を感じさせる人だった。後からわかったのだが、その会社には男性社員は二十代も三十代もいなくて、藤田さんが一番若い社員だったのだ。後に、「年齢=信頼の商売」だと聞いた。
藤田さんに付いて祭壇を準備して、現地まで出向き、運んで飾るところまで全部一緒にやって、何がなんだかわからないうちに一日が終わった。仕事が終わった帰りがけに、
「金ないだろう。飯食っていこうか?」
そのまま居酒屋でおごってくれた。藤田さんの気さくな人柄もあってか今日がバイト初日とはまったく感じない不思議な一日だった。
二日目は祭壇の片づけがあって、また一緒に出て行く。大型のひな壇のような祭壇を組み立て、上物の道具を飾っていく。上物の飾り道具の入った、祭壇の木箱の角には、箱が欠けないように鉄の枠が貼ってある。これで指を挟むと、つぶれるほど痛い。木箱を素手で触るのは危険という意味もあり厳禁、軍手は必須アイテムだ。祭壇そのものに触る飾り片付け時は、軍手からきれいな白手袋に変えるのは、これまた必須だ。道具類を丁寧に扱うことは徹底して指導された。白木の祭壇に手垢は厳禁なのだ。
「冨安君、指を挟むなよ。なかの道具は白手袋して、表面が汚れないように裏側を持てよ」
葬具の扱いへの注意をしてくれながら、合間を見ては倉庫で葬祭用の道具類一つ一つの名前や取り扱い方、宗旨宗派のこと、全体の設営や段取りなどを教えてくれた。祭壇は重いものは三十キ四十キロ。無垢のケヤキの祭壇などは五十キロくらいのものもあって、二人でないと持てない葬具ある。
いろいろな家を訪れて、朝から晩まで三日間、組み立ててはバラし、組み立ててはバラす。そんなことを繰り返していたら、祭壇の種類が違っていても組み立て方の基本は同じなので、だいたいは一人でもわかるようになってきた。ただ、仏式の祭壇はよく出るので、すぐに覚えたが、神道や創価学会やキリスト教の祭壇や設営・段取りは滅多にないから、出来る限りのメモをし、忘れないようにしていた。すべてが見たこともない事だったので、僕には新鮮に感じ、なぜかもっと知りたい好奇心が沸き起こり楽しかった。
「短期間のアルバイトなのに、冨ちゃん、熱心やのぉ」
藤田先輩はいつも微笑みながら言ってくれていた。
*
そして、僕の人生の運命を決めることになる、バイト四日目が来た。前日に葬儀は終わっている家。その翌日の出来事だ。当日は、出棺時間が最終の火葬場の窯の受付だったので、外まわりの受付道具や提灯、テントや庭飾りなどを片づけて、家のなかのメイン祭壇は初七日まで使用したので、片づけは次の日になったのだ。
「中の祭壇を片づけに行くぞ。それが終わったら、俺は明細書を説明して、集金もしてくるから、祭壇の片付けが終わったら車で待っててくれ」
この日の朝、藤田さんは僕にそう声をかけてトラックに向かった。現地で祭壇を片づけて部屋を元の状態に戻し、清掃までが終わると、集金がある場合はいつもは「車で待ってろ」となるのだが、その日は、
「お茶を出してくれるそうだから、そこの縁側で飲みながら待っていてくれ」
と言われて、僕は縁側に腰をかけて待つことになった。お茶とお茶菓子が家族から出された。先輩は縁側奥の座敷のなかで集金を始めた。僕は縁側で外を向いてお茶を飲みながら、「いったい藤田さんが何を話すのだろう?」と興味津々、座敷のほうに聞き耳を立てていた。
請求書の明細を見せながら一つずつ説明していく中、
「藤田さん、本当に良いお葬式だったよ。ありがとうございました」
遺族の声が聞こえてくる。僕もこれまで数々のアルバイトをしてきたが、どんな仕事でも普通は、お金をもらうほうがお客様に、「ありがとうございました」と言って頭を下げるものだ。ここではお客様のほうが、「ありがとう。ありがとう」と言っては、何度も頭を下げている。
「なぜなんだ! どうして?」
その光景は、僕にはものすごく不思議に思えた。
藤田さんの声が聞こえる。
「お飾りした祭壇は~。この金額で、返礼品の数は・・・・・・、百五十五個になりますが、一つが五百円ですから。ドライアイスは二回入れましたので。最初にお邪魔した夜に一回入れさせていただいて、もう一回は納棺の時に入れさせていただきました」
藤田さんが一所懸命説明しているのに、遺族はそんな説明なんてどうでもいいかのように、感謝の言葉が飛び交う。
「藤田さん、ほんとにね、(亡くなった)親父、喜んでると思うよ! あんたに担当してもらってよかった! あんなに丁寧にしてもらって、本当に助かったよ。ありがとうな」
喪主の息子さんが言うと、居合わせた遺族も口々に感謝の言葉を藤田さんに向けている。
「親戚の手前、俺も長男としてきちんと役目果たせたし・・・」
喪主の方と思われるその人の顔は安堵感に満ちていた。「藤田さん、あんたすごいね、若いのにしっかりしてるねえ」
喪主の奥さんと思われる女性の声がした。(へぇ~、藤田さん四十歳過ぎているのに若いって言われるんだ)と感心していると、亡くなられたおじいちゃんの連れ合いだったおばあちゃんが、
「私のときも藤田さん、あんたにやってもらいたいからのう。だから、絶対指名するからね。おじいちゃんと同じようにお願いね・・・・」
大粒の涙を流しながら、藤田さんの手を両手で握りながら、心から嬉しそうに言っている。まるで孫にでも頼んでいるかのようだ。
「親父は働きづめでね、なんにも親孝行してやれなかった。でも最期だけ、あなたに手伝ってもらって、良い親孝行ができたけぇ。ちゃんと最期に、親父、ありがとう、って言えたよ・・・・」
喪主の方の目は涙で膨れていた。
「藤田さん、ほんとにあなたに救われたような気がしますよ。ありがとうね」
奥様も涙を浮かべながらに言う。もう先輩が説明している声よりも、遺族が感謝している声しか聞こえてこなかった。そして、「ありがとう」と言いながら、集金のお金を差し出す喪主。見ていたら二百万円近くの大金である。集金が終わってからも、
「藤田さん、こっちのほうに来たら遊びにきてね。気にせず立ち寄ったってね」
親戚のお兄ちゃんにでも言うように別れ難そうに言っている。
「はい。法事のこともありますから、またパンフレットもって説明にきますからね」
温かなやりとりが続いていた。
*
強烈で、鮮烈な光景だった。心の底から感謝をされて、「ありがとう、ありがとう」と言われながらお金を受け取る。こんな仕事がほかにあるだろうか。なんだか逆さまだぞ!
このときの経験は、僕にとって衝撃のシーンであった。ものすごい違和感を覚えると同時に、こんなに感謝されるのはなぜだろう?と不思議な気持ちになった。藤田さんは遺族に対して、この二日間に何をしてあげたのだろうか、どうしてもそれを知りたくなった。
このありがとうで埋め尽くされたあの場面のもとにある人の心を感謝と感動で溢れさせる未知なる世界をもっと知りたくなったのである。
アルバイトの僕の仕事は片づけと飾りつけだけだったので、その未知の世界に触れていなかった。アルバイトの仕事は遺族と触れ合っているようで触れ合っていない。人のいないところで葬具を設置したり、片づけたりしていただけで、打ち合わせのやり取りも式の流れも見ていない。出棺のとき、最後に霊柩車が出ていくのを遠巻きに見ていて、散会しはじめたらトラックを近づけて片づけに入るだけ。依頼を請け負い、打ち合わせのところから入る、遺族との触れ合いという一番のところは何も見ていなかった。
縁側の端から感謝と感動が溢れる衝撃のシーンを見たときに、幼い頃から「人のために生きなさい」と言われ続けた僕は、藤田さんがなぜここまで遺族の人たちの心をつかんで感謝されているのか、知りたくて矢も盾もたまらなくなってしまった。
「ここを出たら、すぐ藤田さんに聞こう!」
助手席に乗り込み車が動き出すやいなや、すぐ藤田さんにその質問をした。
「どうしてご遺族はあんなに藤田さんのことを褒めているのですか? 涙ながらにありがとうって感謝してるんですか? おばあちゃんは自分の死んだ時のことまでたのんでいたじゃないですか?」
僕は溢れ出る質問を矢の如く投げ掛けた。
「おいおい、何だよ急に」
とびっくりした顔で僕を見たあと、エンジンを掛け、その家を後にした。その後に藤田さんはゆっくりと語り始めた。
「この仕事はね、冨安君、日常的に起こることじゃないこと、起こってほしくないことが起き、しかも大切な人を亡くして、悲しみで途方にくれているときに、どうすればいいのかを丁寧に教えてさしあげる仕事なんだ。この世にたった一人の大切な方を滞りなくお見送りするという儀式を、一つ一つ懇切丁寧にわかりやすく導いてあげなければならないんだ。葬儀社っていうのは、遺族の悲しみや故人への想いを感じながらやれば、親戚以上に頼りにされる存在なんだよ。
大切な人を送るという最終最期のときに、家族は悲しみに打ちひしがれていてどうすればいいのかわからない。それを知っている俺のような担当者によって戸惑わないように、滞りなく手伝ってもらえるということがいかに心強いか、頼られる存在になれるか、そういうところが俺たち担当者の仕事にはあるんだよ。
たった二日間のことなんだけど、悲しみで途方にくれているなかで、ちゃんと家族を送れた、長男として、喪主という大役を果たし、親をちゃんと送れたっていう安堵感に浸れたとき、心から安心し、喜んでもらえる。俺らは、心から感謝される存在になれるんだよ」
信号が青に変わったので発進操作をしながら、藤田さんは、ポツリとつぶやくようにつけ加えた。
「冨安君、たぶん、一生忘れないよ。あの人たちは・・・、俺のことを」
遺族の人々に感謝されていた、先ほどの光景がまた浮かんできて、僕はしびれるほどの感動を覚えていた。鳥肌が立っていた。心の中に激震が走った。
(わあ、すごい! 人の心をこんなに動かし、感動させられる仕事があったんだ)
人間はどこかで誰かに感謝されたいとか、頼られたいとか、褒められたいという本能に似た気持ちを持っている。それがこの仕事にはあると考えたとき、瞬間的に「藤田さんみたいになりたい!」と心の底から思った。高校一年生の夏休みにアルバイトで稼いだお金で土佐の高知に渡り、坂本龍馬の銅像の前で、「僕にも絶対何かやることがありますよね」と両手を合わせたときから考えていた。
幕末の頃、時代を変えようとしていた若者たちは、十代、二十代だった。その時代の在り方を根本から動かそうとしていた人々はみんな若かった。僕は十八歳、その年の七月が来たら十九歳になる。龍馬像の前で誓った「人生において、絶対何かやることを見つけるぞ」ということが、あれ以来ずっと頭のなかにあった。
バイトを始めて四日目、僕は運命の仕事に出会った。